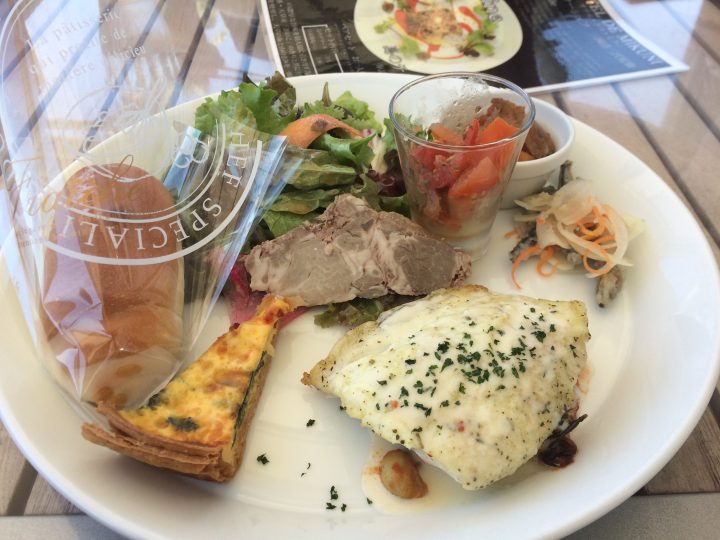小さな会社のイノベーション(経営革新)
企業が成長局面にある時、さまざまなイノベーション(革新)を経過する必要があります。
イノベーションを経過せずに、成長はないと言っても過言ではないでしょう。人間もそうですよね。成長するためには、”変革=革新”していかなければならない…のです。
特に中小企業は、イノベーションをいかに起こすか?その一歩がとても重要です。
しかし、その一歩がなかなか踏み出せない…。理由はさまざまですが、往々にしていあるのが、以下の数点に集約されます。
①何かを起こさないと(何か変えないと)いけないことは分かっているけど、何を変えればいいか分からない。
②何となく、やるべきことは見えているけど、いつ始めていいか分からない。
③始めたいことは明確だけど、資金がない(そのため、設備投資できない)。
④始めたいことは明確だけど、具体的なシミュレーションが立てれない。
⑤始めたいことは明確だけど、ヒトがいない(マンパワーがたりない)。
だいたいこんなところでしょうか?
もっとも多いのが、①〜③だと思いますが、意外と解決策があるものです。
コンサルタントの立場から言いますと、もっとも必要なのは経営者の”カクゴ(覚悟)”です。
覚悟があれば、まずはもっともエネルギーを使うキックオフはできます。
そのエネルギーを充填させるプロセスにおいて、入念な準備をしていけばいいのです。
企業が成長局面にある時、さまざまなイノベーション(革新)を経過する必要があります。
イノベーションを経過せずに、成長はないと言っても過言ではないでしょう。人間もそうですよね。成長するためには、”変革=革新”していかなければならない…のです。
特に中小企業は、イノベーションをいかに起こすか?その一歩がとても重要です。
しかし、その一歩がなかなか踏み出せない…。理由はさまざまですが、往々にしていあるのが、以下の数点に集約されます。
①何かを起こさないと(何か変えないと)いけないことは分かっているけど、何を変えればいいか分からない。
②何となく、やるべきことは見えているけど、いつ始めていいか分からない。
③始めたいことは明確だけど、資金がない(そのため、設備投資できない)。
④始めたいことは明確だけど、具体的なシミュレーションが立てれない。
⑤始めたいことは明確だけど、ヒトがいない(マンパワーがたりない)。
だいたいこんなところでしょうか?
もっとも多いのが、①〜③だと思いますが、意外と解決策があるものです。
コンサルタントの立場から言いますと、もっとも必要なのは経営者の”カクゴ(覚悟)”です。
覚悟があれば、まずはもっともエネルギーを使うキックオフはできます。
そのエネルギーを充填させるプロセスにおいて、入念な準備をしていけばいいのです。
投稿日: 2017年11月27日 | 9:58 pm