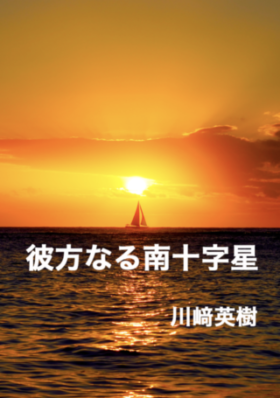診断士こそホームページを開設せよ!
中小企業診断士はとは何ぞや?そんな疑問を今更ながらに考えています。中小企業診断士の本分は「国家資格を持った中小企業専門の経営コンサルタント」だと言えます。
中小企業専門の経営コンサルタントは?抽象化した考え方をあえて言うと、「中小企業の経営状態を向上させるために、伴走型で支援する専門家」です。
中小企業診断士の登録者数は3万人弱と言われています。困っているクライアントが支援を依頼したいと考える時、何を判断基準にしたらいいか…?迷うことも多々あると考えています。
なぜなら、中小企業診断士の情報発信が圧倒的に少ないと感じるからです。
法律的な手続きに縛られる他の士業と違って、中小企業診断士の攻撃守備範囲は広い。無限大と言ってもいいでしょう。
中小企業診断士は、その主張が大切です。さまざまな経営に対する価値観を発信するためにも、ホームページを解説して断続的に情報発信していきましょう。
また、診断士にも得意分野があります。それこそ多様性に富んでいます。
僕のような「ブランディング」や「マーケティング」が得意な診断士。「経営改善や事業再生・企業再生」が得意な診断士。「助成金・補助金申請が得意な診断士」…本当にさまざまです。
特に分野とクライアントのニーズがマッチして仕事をするのが理想ですので、我が主張をホームページで発信してくことはマストです。
昨今はホームページ開設と運用がとても大切です。情報発信はオンリーワンポイント訴求する手段として、取り組むべき経営課題と言えるのです。診断士も一緒です
【お知らせ】
毎週金曜日に配信してるメルマガ「赤ひげ診断士のアウトロートーク」で、コンサルティングのノウハウを無料ダウンロードできるようになりました。自身のコンサルティングや、自社の経営にお役立ていただければ嬉しいです。
https://www.mag2.com/m/0001693674
中小企業診断士はとは何ぞや?そんな疑問を今更ながらに考えています。中小企業診断士の本分は「国家資格を持った中小企業専門の経営コンサルタント」だと言えます。
中小企業専門の経営コンサルタントは?抽象化した考え方をあえて言うと、「中小企業の経営状態を向上させるために、伴走型で支援する専門家」です。
中小企業診断士の登録者数は3万人弱と言われています。困っているクライアントが支援を依頼したいと考える時、何を判断基準にしたらいいか…?迷うことも多々あると考えています。
なぜなら、中小企業診断士の情報発信が圧倒的に少ないと感じるからです。
法律的な手続きに縛られる他の士業と違って、中小企業診断士の攻撃守備範囲は広い。無限大と言ってもいいでしょう。
中小企業診断士は、その主張が大切です。さまざまな経営に対する価値観を発信するためにも、ホームページを解説して断続的に情報発信していきましょう。
また、診断士にも得意分野があります。それこそ多様性に富んでいます。
僕のような「ブランディング」や「マーケティング」が得意な診断士。「経営改善や事業再生・企業再生」が得意な診断士。「助成金・補助金申請が得意な診断士」…本当にさまざまです。
特に分野とクライアントのニーズがマッチして仕事をするのが理想ですので、我が主張をホームページで発信してくことはマストです。
昨今はホームページ開設と運用がとても大切です。情報発信はオンリーワンポイント訴求する手段として、取り組むべき経営課題と言えるのです。診断士も一緒です
【お知らせ】
毎週金曜日に配信してるメルマガ「赤ひげ診断士のアウトロートーク」で、コンサルティングのノウハウを無料ダウンロードできるようになりました。自身のコンサルティングや、自社の経営にお役立ていただければ嬉しいです。
https://www.mag2.com/m/0001693674
投稿日: 2022年2月22日 | 5:59 am